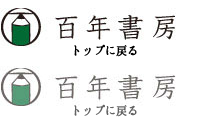日本考古学界の重鎮、大塚先生は今年89歳。いまも現役でご出身の明治大学リバティアカデミー、朝日カルチャーセンターなどで講義をされていらっしゃいます。1年前から始まった私家版の自分史はなかなか出来上がりませんが、今日は途中経過、執筆中の苦労話などをお聞きしました。(聞き手 百年書房・藤田/2015.12更新)

1926(大正15)年東京生まれ。明治大学名誉教授。日本考古学協会会長、登呂遺跡再整備検討委員会などを歴任。主な著書に『邪馬台国をとらえなおす』(講談社現代新書)、『弱き者の生き方』(五木寛之氏との共著・毎日新聞社)などがある。弥生時代から古墳時代がご専門。
- ―――
- 本日はお忙しいところ、ありがとうございます。お具合はいかがですか?
- 大塚
- 今回は腎臓がよくないっていうんで、2週間ほど検査入院に行ってきました。
- ―――
- 講義と講義の合間をぬって、なんですよね?
- 大塚
- そうです。講義の予習もしなくちゃいけないから病院でやってね。
- ―――
- 89歳で…年齢のことを言うと失礼になりますけれど、いまも現役バリバリで講義をされているのは本当に凄いことだと思います。こうして大塚先生と話をさせていただいていて驚かされるのは、固有名詞がズバズバ出てくるところなんです。
- 大塚
- いや、これでもね、衰えたなっていうところはありますよ。以前はもっとパッパパッパと出てきましたから。たとえば安本美典(邪馬台国の研究者)の名前がすぐ出てこなくなったりしてね。それでも割と覚えているほうかな? 僕の場合はね、フルネームで言えるのが自慢なんです(笑)。
- ―――
- フルネームでおっしゃいますもんね。講義には時間をかけて予習をされていると聞きました。
- 大塚
- 予習しないと追いつかないんですよ。
- ―――
- そんなことないんじゃないですか!?
- 大塚
- これ、本当です。僕がいま講義しているリバティアカデミーとか朝日カルチャーっていうのは、60代70代のご年配が中心ですけど、リタイヤして趣味で勉強している方々だから物凄くいろいろとよく知っているの。昔取った杵柄じゃないけれども、古い知識で講義していたら立ち往生しちゃいます。「先生、先月こんなことがありましたが…」って言われて、最新の考古学事情に精通しておかないと対応できない。
- ―――
- その緊張感が、大塚先生の元気の源になっているのかもしれませんね。
- ―――
- 大塚先生の自分史プロジェクトが始まって、もうすぐ1年になります。
- 大塚
- 忙しくてなかなか進まなくって。
- ―――
- 遅々とではありますけど進んでいますから、少しだけスピードアップしていただいて…。いまのところ、いかがですか?
- 大塚
- 自分のことを書くのは難しいね。研究のようにテーマがあるわけじゃないから。
- ―――
- 「ご自身がテーマ」ということになります。
- 大塚
- そう、だから難しい。何と言うか、どこかに発表する論文とは別の難しさがあるわけです。
- ―――
- 十分にお上手ですよ。というよりも何度も申し上げている通り、上手でなくてもいいのです。大切なのは何を書くか?ですから。
- 大塚
- そうでした。
- ―――
- まずは残す、ということが一番ではないかと思っています。たとえば大森貝塚という遺跡があります。
- 大塚
- エドワード・モースだね。
- ―――
- 縄文時代の遺跡ですけれども、もともとは…
- 大塚
- 縄文時代のゴミ捨て場。
- ―――
- そうなんです。ゴミ捨て場にたとえるのも何ですけど、残っているからこそ意味があると思うんです。残ったものをどうするかは後世の人たちに任せると言いますか。
- 大塚
- 残したものの価値は、残された人が決める。たいへんな資料になることだってあるからね。
- ―――
- なるかもしれないし、ならないかもしれない。でも、まずは残す。だから上手だとか下手だとかは問題ではないと思います。たとえば子孫が自分を知る、先祖を知るための資料を残すと言いますか。
- 大塚
- 江戸時代の書物などは、天候が書いてあるだけで貴重な資料になっているわけだからね。
- ―――
- たとえば大塚先生からお手紙をいただくことがあります。するとそのお手紙は再利用といいますか、出版社からもらった原稿用紙を便箋がわりにお使いになっています。で、お手紙が入っている封筒もやはり朝日カルチャーの封筒などをお使いになっている。大先生で、お金もあるのに物をたいへん大切にされる方です。
- 大塚
- うん、大切にしますね。
- ―――
- ではどうして大切にされるのか? 大塚先生は戦争を体験されていて、九死に一生を得たというか、価値観ががらりと一変したというか、さらに戦後は極貧生活の中でお母様をなくした…そういう体験をされています。ただケチだから便箋封筒を再利用するわけじゃない。そこに物語があるわけです。大塚初重はこんなことがあったから、もしかするとこんな人になったよ、という物語。大塚先生は自伝的なご本もすでに上梓されています。『土の中に日本はあった』(小学館刊)、『日本列島発掘史』(KADOKAWA刊)などがそうです。
- 大塚
- 自伝的な本だね、あの2冊は。
- ―――
- あの2冊からこぼれ落ちたような話が、もっともっとあると思っているんです。考古学のお仕事的な部分での大塚先生を知る本はあります。もっと私的な部分、これまでの著書で書かれなかった部分が出てくると、いま私たちが作ろうとしている私家本の意味というものが出てくるのではないかと思います。
- 大塚
- そうだね。抜け落ちた部分っていうのはあるし、何より最近、考古学界の先生がたがどんどん亡くなっているんです。取り残されるって言ったらおかしいけれども。今年、江坂輝弥っていう96歳の考古学の元慶応大学の先生が亡くなりました。この江坂先生とはね、特別に思い出があります。昭和24年8月に下北半島で発掘調査している時にね、江坂先生のあとをね、女の子が一緒について来ちゃったんだ。
- ―――
- 追っかけみたいな感じですか?
- 大塚
- 当時は中学生じゃなかったかな。
- ―――
- えっ…それは問題ですね。
- 大塚
- まずいんです。私の兄弟子である杉原荘介先生に「大塚、お前、女の子が泊まる旅館を探してこい」って言いつけられてね、自転車で探し回ったことがあるんです。なんで俺が探さなきゃいけないんだって思ったけど、杉原先生の命令だったからね。その女の子が後の江坂先生の奥さんになった人。奥さんは江坂先生よりも先に亡くなったけど。
- ―――
- 大塚先生、キューピッドじゃないですか。
- 大塚
- そう。訃報を聞いてそんな出来事を思い出したりしてね。この話なんかはどこにも書いていないんだよね。
- ―――
- 大御所の大塚先生が下っ端だった頃の話(笑)。
- 大塚
- そう。いろんな話があるんだよ(笑)。
- ―――
- そういう話をどんどん書いてください。卒寿(90歳)のお祝いに本が間に合いますように…。
- 大塚
- それです。
- ―――
- 引き続きどうぞよろしくお願いします。本日はお忙しいところ、ありがとうございました。